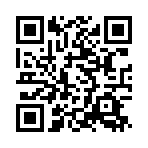タガメ料理のリクエスト
メンダーとはタガメのことです。これを発酵調味料や唐辛子その他の香草と一緒に潰して作るディップソースは都市の人にも人気があって普通に市販されていますし、値段も高目。東北の人ですと、焼いてそのまま食べるのが好きな人ももちろんいます。香水のような強い人工的な香りがして自然の驚異を感じます。で、このメンダーですが、俗語で「ヒモ」のことでもあります。メスがオスを背中に乗せたまま餌をあさるなどの活動をするのに由来するとか。「メンダー」は日本人の発音でもまず通じますから、覚えておくと便利なタイ語…なんてことは、ないか。なお、そのお客さんのために食材屋さんからメンダーを仕入れたことは言うまでもありません。
2009年06月25日 Posted by namfon at 17:38 │Comments(13) │食材の話題
辛い料理には生野菜が付き物
ここにあるのは、清涼感漂う香り豊かで私の大好きなパクチー・ラーオ(ラオスパクチー)とキュウリ以外は初対面。調べてみないといけませんね。野菜もハーブもアクも好きなので最初から抵抗はありませんでしたが、ちょっとびっくりしたのはバナナの花です。パッタイの付け合せに欠かせないものですが、栗の渋だけで花にしたような強烈な渋さ。最初はびっくりしました。アクとガンの関係も取りざたされたこともあったな、などと。きっと苦手な方には辛い食生活だと思いますが、アク抜きするのがもったいないと感じたことがあったり、アクの強い山菜や野草が好きという方ならタイ料理好きの素質は充分だと思います。
2009年06月22日 Posted by namfon at 21:19 │Comments(6) │タイ料理の話
東北地方独特の腸詰豚ソーセージ
バンコクの屋台で、豪快な煙を上げて炭火で焼きながら売っているのをビニール袋に入れてもらって、歩きながら唐辛子とニンニクとキャベツの葉っぱをかじりながら、このソーセージを食した思い出に浸りながら、東北地方を巡る旅の途中の川辺のしゃれたレストランで注文してみました。メニューには書いてなかったんですが「食べたい」と言ったら出してくれたもの。こういう融通はタイでは常識。チェリーでも材料がある限りはタイの常識で営業しています。このソーセージの特徴はモチ米を入れて発酵させていることで、だから酸味があるのです。白い粒々を最初は豚の脂身だと思っていました。米を入れていると知った時は、貧しいから米で増量しているのかと思いました。ニンニクが入っている上に、ニンニクやらショウガを付け合せるのもいかにもタイ。ビールのつまみに最高です。チェリーではメニューには入れていませんが、時々あります。北部には東北とは違った種類の「サイ・ウア」というのがあって、これもまた最高なんですよね。
2009年06月21日 Posted by namfon at 12:01 │Comments(0) │タイ料理の話
パッタイって何か分らなくなりました
 直訳すると「タイ炒め」の「パッタイ」を好きな方は多く、たまには他をどうですか、と言いたくなるくらいに、こればかり注文する方もいます。そういうひとりに、タイのおみやげの即席パッタイを渡したら「美味しかった」というメッセージと一緒に写真が送られてきました。なかなか美味しそうにできていて、味見できなかったのが残念。各種インスタントタイ料理がいろいろなメーカーから発売されていて、一昔前では考えられないタイ料理の普及ぶりと利便性には目をみはるばかりです。
直訳すると「タイ炒め」の「パッタイ」を好きな方は多く、たまには他をどうですか、と言いたくなるくらいに、こればかり注文する方もいます。そういうひとりに、タイのおみやげの即席パッタイを渡したら「美味しかった」というメッセージと一緒に写真が送られてきました。なかなか美味しそうにできていて、味見できなかったのが残念。各種インスタントタイ料理がいろいろなメーカーから発売されていて、一昔前では考えられないタイ料理の普及ぶりと利便性には目をみはるばかりです。ネットで作り方を検索したらたいていのタイ料理は作れてしまう世の中でもありまして、そのせいで湧き上がっている疑問がこのパッタイについてです。作り手によって作り方にバリエーションがあるのは当然とはいえ、それにしてもパッタイと呼ぶのはタマリンドの絞り汁を入れるもの、との思い込みが覆されつつあるのです。タマリンドのおかげで甘みとほのかな酸味の風味が出るわけで、もちろんチェリーではオリジナルソースを作って正統派(?)パッタイをお出ししています。でもタマリンドなしの炒め麺の作り方が「パッタイ」としてブログなどで紹介されていますし、お店によっても同様。何をもってパッタイと呼ぶか、思い込みを検証してみようと思います。いずれにしろ食べ比べてお好みを選べるようになったのは楽しいことです。
2009年06月20日 Posted by namfon at 17:12 │Comments(0) │タイ料理の話
タイ料理の4区分
タイの書店でまさに「4つの地方料理」という本を見つけたので買ってきました。「タイ人は身近で入手できる食材を使うので地方色が豊か」から始まります。北部は海から一番遠いので海魚は使いません。あまり辛みは強くなく、野菜の自然の甘みを利用する。東北地方は川魚や昆虫色も盛んなので匂い消しの意味もあって香草や唐辛子を多用。南部はシーフードを使って辛みが強め。中部は海もあって穀物地帯でもあり食材が豊富で料理も多彩。そんな特徴を頭の隅においてタイ料理店のメニューを見てみると、その店の方針というか得意分野が想像できて、楽しみも一段アップすると思います。ちなみに写真は分類したら中部料理のゲーン・リエン。魚のダシでショウガ味の効いた野菜と香草たっぷりのスープ。日本では作りにくいのが残念です。
2009年06月14日 Posted by namfon at 14:06 │Comments(0) │タイ料理の話
日本人はカレー味がお好き?
日本のカフェにもありそうな白い器。ココナツミルクの入ったカレースープに揚げた麺ですから、薬味を入れてライムを搾ってもやはりちょっとしつこい感じです。辛みも足りない。若い人にはいいのかもしれませんが、しばらくお腹が重たくなりました。日本語のタイ料理本を見ていたら「私の知っている日本人でカーオ・ソーイを嫌いな人はいません」というタイ人の著者のコメントが…。カレー味は確かに日本人には人気がありました。シーフードレストランだと「カニのカレー炒め」が代表。これはバーン・チェリーにもあって、ボリューム満点なので数人のグループだったら特にお勧めです。カニをエビに変えることもできます。
2009年06月08日 Posted by namfon at 20:18 │Comments(0) │タイ料理の話
フレッシュなジュース屋がどこにでも
タイ人は運転席から出て行くこともまずしませんから、窓をあけて「2本ちょうだい」と大声で注文。ところが何度言っても、聞こえないようで3本渡そうとします。ま、いいかで受け取りました。たったの10バーツですからね。氷の中に入れて冷やしてあるので自然の味そのままでとっても美味しい。砂糖キビジュースは甘いのですが、本州ではまず生の搾り立てを飲むなんてことはできないので、タイに行くと1度は飲みます。暑いなあ、と思いながらバスを待っているバス停の脇にもよくあって便利。ただ今回の旅で感じた変化は販売員の高齢化です。少子高齢化はタイでも急速に進んでいるのは感じてましたが、こんなところにも。日本でも自動販売機を減らして、人的対面販売を普及させたら失業対策の一助になると思うのですが、保健衛生上の規制が厳しいからトラックの移動販売がいいところですね。
2009年06月07日 Posted by namfon at 11:21 │Comments(0) │タイの食べ物
タイ風にするためのスープストック
家でタイ料理を作る場合、タイ風のスープを作っておくといいわけですが、わざわざ作らなくても例えば鍋物やしゃぶしゃぶなどを夕食にしたら、そのスープにコリアンダーの根っこ、ニンニク、タマネギを入れるとタイ風になりますね。この間、たまたま固くなったセリの茎を捨てるのももったいないくてスープに入れてみたら、なんとなくタイの味っぽくなりました。もっとも日本のセリと同じものをタイで見たことはないですが。他にも香りの強い野菜をスープに入れて工夫するのも面白いかも、と思った次第です。このスープにトムヤムペースト、グリーンカレーペースト、レッドカレーペーストを入れたらすぐにタイ料理の出来上がり!お試し下さい。写真は本文に関係なく、ビエンチャンで食べたラーメン。スープが別になってました。ライムがついてくるのは珍しかったです。