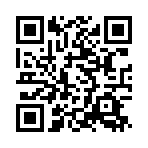来年のイナゴの季節に
和風のイナゴ料理は甘辛い煮つけがほとんどのようですが、大量に採れた場合のバリエーションとしてタイ風もいかがでしょうか。濃い味にすると失われがちなイナゴの風味が生き生きしていてオツです。オヤツにぽりぽり食べたり、もちろんおつまみにも。小さなお子さまの口に入れてあげる際は足をもいであげると、喉へのひっかかりが防げます。バンコクの屋台では、大きなフライパンで揚げながら売っています。屋台のイナゴは日本のものが赤ちゃんに感じるくらいに大きかったのですが、あれはバッタだったのかもしれないと今になると思います。今度行った時に確認してみます。
2009年09月26日 Posted by namfon at 19:03 │Comments(2) │食材の話題
カーだぞ!
何に使うかというと、代表は「トムヤム」です。「トムカー」という、トムヤムと同じ風味のココナツミルクのスープにもたっぷりと入れます。その他いろいろ、タイ料理には欠かせない素材です。タイ料理の調理法は「切る」よりも「叩く」が基本になっていますが、それはこのカーのおかげじゃないかと思ったりします、ひとたたきで香りが立ち風味も豊かに。切るよりぶっそうじゃないし、信念ある平和的にも感じるカーの力の思い出ですが、しかし見れば見るほど近未来的、ロボット的にも思えます。
2009年09月05日 Posted by namfon at 12:59 │Comments(2) │食材の話題
パクチーの根の一口解説
根の使い道はスープストックに入れる、スープ類に入れる。パクチーの根が入ったままのトムヤムが運ばれることもあると思いますが、ダシのひとつなのでムリして食べることはありません。スープ以外では、「ヤム」というサラダ類に根っこを潰して使います。パクチーの根と唐辛子とニンニクをポクポクとクロックとサークでしっかり潰し、ナムプラーとレモンで好みの味に整えて、焼いた肉でもシーフードでも春雨でも、ミックスした具でも何でも、好きな具をタマネギやセロリやキュウリなどと一緒にこのドレッシングで和えます。今の季節なら焼きナスにこのドレッシングをかけても美味。油を使わないしダイエットにもよろしいと思います。ついでにタイ語で根のことは「ラーク」。パクチーの根は「ラーク パクチー」となります。
2009年08月05日 Posted by namfon at 09:55 │Comments(1) │食材の話題
トムヤム用ハーブはセット販売
これが有名な「トムヤム」というスープに必要なハーブセットで、日本のタイの食材店でもだいたいこうしてセットにしてあります。香りが出やすいようにたたいたり切れ目を入れたこれらハーブをトリガラスープに入れて、好きな具を入れて、唐辛子とレモン(タイではライムですが…)を入れたらトムヤム完成。そういえば唐辛子とレモンはセットに入ってないのはなぜだろうと考えて、タイ人のキッチンから唐辛子とレモンとニンニクが切れるなんてあり得ないから、あえてセットにすることもないんだろうと思いました。最近はタイ料理のインスタント食品も充実して乾燥ハーブが添えられていたりもしますが、できればフレッシュなハーブを足すと本格的。タイの食材店ならトムヤムセットがないということはまずありません。
2009年08月03日 Posted by namfon at 14:14 │Comments(0) │食材の話題
唐辛子抜きにタイ料理は語れない
写真はバンコクの市場の様子です。唐辛子の種類も多々ありまして、用途に応じて使い分けます。例えば有名な「グリーンカレー」。こちらはグリーンの唐辛子を使います。グリーンほど有名ではないようですが、私はこっちの方が好きな「レッド・カレー」は赤い唐辛子を使うのでこの名前。激辛で知られる小さな唐辛子「プリック・キー・ヌウ」は、日本語にすると「ネズミの糞の唐辛子」です。キーが糞で、良くない意味の熟語用に大活躍です。キー・ニャオは「ケチ」、キー・ガオは「寂しがりや」、キー・マオは「酔っ払い」、キー・ゴーホックは「嘘つき」、その他いろいろありますね。
2009年07月23日 Posted by namfon at 23:51 │Comments(2) │食材の話題
パクブンが育っています
空芯菜は日本でも普通に栽培されるようになっているようで、夏場は市場に出回りますね。タイ料理の代表は、唐辛子とニンニクをふんだんに使って炒める「パクブン・ファイデーン(炎の空芯菜)」。ごくごく簡単でビタミン豊富な料理ですから夏バテ防止用にも作ってみて下さい。タイではスープに入れたりと、日常的に利用する野菜です。葉っぱの長い写真のような種類は畑栽培に適していますが、私の好みは湿地帯に自生する葉っぱの小さな雑草タイプ。山菜のようなほのかな苦味があって、辛い料理と一緒の生食に適しています。この種類は日本で栽培されていないようなのが残念です。もっとも自分で作ってみるべきでしょうか。
2009年07月13日 Posted by namfon at 23:25 │Comments(2) │食材の話題
カラフルな米が日本でも流行るか?
なるほど!どうして日本にはないのだろう、あるいはもうあるのかな、と思って、試しにひとつ購入してきたのが写真のオレンジ色の米で、着色はニンジンで。ちゃんと小さな袋入りが用意してあるのは、さすがに観光客も多いデパートの工夫。何種類も欲しかったのですが、荷物の量も限界を超えていたため、ニンジンのみにしました。ちなみにラジオではその後、野菜で米に色をつけるという話をしていました。どっちが先なのか。友人が炊いてみたところ「色は落ちゃった」ということです。バーン・チェリーで試してみますか…。
2009年07月02日 Posted by namfon at 22:44 │Comments(0) │食材の話題
タガメ料理のリクエスト
メンダーとはタガメのことです。これを発酵調味料や唐辛子その他の香草と一緒に潰して作るディップソースは都市の人にも人気があって普通に市販されていますし、値段も高目。東北の人ですと、焼いてそのまま食べるのが好きな人ももちろんいます。香水のような強い人工的な香りがして自然の驚異を感じます。で、このメンダーですが、俗語で「ヒモ」のことでもあります。メスがオスを背中に乗せたまま餌をあさるなどの活動をするのに由来するとか。「メンダー」は日本人の発音でもまず通じますから、覚えておくと便利なタイ語…なんてことは、ないか。なお、そのお客さんのために食材屋さんからメンダーを仕入れたことは言うまでもありません。
2009年06月25日 Posted by namfon at 17:38 │Comments(13) │食材の話題
代用するもの、しないもの
 写真はタイのナスの一種(มะเขือเปราะ=マクアプロッ)です。実が締まっていて歯ごたえ良く生で辛いタレをつけて食べるのも美味しいですし、スープの具にもよく使います。典型的なのはグリーン・カレー。これを日本のナスで代用すると触感がかなり違いますが、夏になると在日タイ人が栽培したり、直売所でたまあに地物を見かけるようになったとはいえ、お店でたくさん使うには高価過ぎて、チェリーのグリーンカレーには、通常は日本のナスが入っています。つまりナスは代用品で諦めるかな、というところ。
写真はタイのナスの一種(มะเขือเปราะ=マクアプロッ)です。実が締まっていて歯ごたえ良く生で辛いタレをつけて食べるのも美味しいですし、スープの具にもよく使います。典型的なのはグリーン・カレー。これを日本のナスで代用すると触感がかなり違いますが、夏になると在日タイ人が栽培したり、直売所でたまあに地物を見かけるようになったとはいえ、お店でたくさん使うには高価過ぎて、チェリーのグリーンカレーには、通常は日本のナスが入っています。つまりナスは代用品で諦めるかな、というところ。一方、代用できずに輸入品に頼っているものが何かというとหอมแดง(ホーム・デーン)というニンニクよりも小型の玉ねぎ。「ホーム」の意味は良い香りで「デーン」は赤ですから直訳すると「赤い香り」となります。名は体を表していて、これを日本の玉ねぎで代用すると料理が別物になってしまうんですね。でもこっちもとっても高コスト。普通の玉ねぎを使っているお店も多く、その気持ちは分かります。この間、野菜作りを趣味にしている方がいらして、この玉ねぎに興味をもって「ちょっと分けて」ということで2粒お持ちになりました。成功を祈っているところです。なお、赤い香りが活躍する料理の代表はลาบ(ラープ)という東北地方の郷土料理です。肉をたたいて細かくして炒ってから多彩な香辛料で和えるものでおつまみにぴったりです。
2008年08月27日 Posted by namfon at 09:42 │Comments(5) │食材の話題
豆下さい、身体下さい
 昔昔、アメリカにホームステイしていた友達が帰国して、野菜でも何でも巨大だと驚いていたのを覚えていますが、タイで驚いたのは、何でも小さいことでした。きゅうりも白菜もナスもみんな小さい。でもインゲンは違います。長いです。50cmくらいあります。タイだと年中出回っていて、辛いタレをつけて生で食べたり辛目に炒めたり、ソムタムのようにたたいたり、辛い料理の付け合せにしたりで毎日のように食べていたものですが、日本で入手はムリと思っていたら松代のマリーさん、見事に栽培してくれました!→写真参照。正式名称はถั่วฝักยาว(トゥア・ファク・ヤーオ)。トゥア=豆、ファク=鞘、ヤーオ=長い。すなわち長サヤインゲン。
昔昔、アメリカにホームステイしていた友達が帰国して、野菜でも何でも巨大だと驚いていたのを覚えていますが、タイで驚いたのは、何でも小さいことでした。きゅうりも白菜もナスもみんな小さい。でもインゲンは違います。長いです。50cmくらいあります。タイだと年中出回っていて、辛いタレをつけて生で食べたり辛目に炒めたり、ソムタムのようにたたいたり、辛い料理の付け合せにしたりで毎日のように食べていたものですが、日本で入手はムリと思っていたら松代のマリーさん、見事に栽培してくれました!→写真参照。正式名称はถั่วฝักยาว(トゥア・ファク・ヤーオ)。トゥア=豆、ファク=鞘、ヤーオ=長い。すなわち長サヤインゲン。バーン・チェリーで仕入れているのは目撃したのですが、どう料理するのかは謎。スタッフの賄い料理になってしまわないうちに興味のある方は注文してみて下さい。でも発音は気をつけて下さいね。トゥア=豆の部分は特に要注意です。カタカナ表記すると豆も身体もチケットも同じなんです。違うのは有気音か無気音かと声調。バンコク在住時に友人(男)が旅行会社に行って「チケット下さい」と言ったつもりが「身体下さい」と若い女性スタッフに向かって言って憤慨されたそうです。チェリーのスタッフでそれで怒る人はいないと思いますが、息を出してしっかり発音するのがコツです。なお、長インゲンが手に入らないと日本のインゲンを生食してます。多少生臭さが強い気はしますが同類の味です。
2008年08月08日 Posted by namfon at 23:34 │Comments(0) │食材の話題
夏野菜のシーズンです
 長野ってタイ人が結構多いのです。県の外国人登録人口を見ていただけると分かりますが、地方都市の割には多い方。たいていが日本人と結婚している人ですね。ということは…。長野ですから配偶者はたいてい畑があります。プラス、長野在住タイ人は農村出身者が多い。イコールタイの野菜を作る、というわけで、夏はバーン・チェリーにとっては嬉しい季節です。夜になると自分で栽培した野菜を売りにタイ人たちが訪れます。新鮮なパクブン(空心菜)、パカナ、タイのナス、タイのインゲンの地場物が続々と。パクチーはもちろん。
長野ってタイ人が結構多いのです。県の外国人登録人口を見ていただけると分かりますが、地方都市の割には多い方。たいていが日本人と結婚している人ですね。ということは…。長野ですから配偶者はたいてい畑があります。プラス、長野在住タイ人は農村出身者が多い。イコールタイの野菜を作る、というわけで、夏はバーン・チェリーにとっては嬉しい季節です。夜になると自分で栽培した野菜を売りにタイ人たちが訪れます。新鮮なパクブン(空心菜)、パカナ、タイのナス、タイのインゲンの地場物が続々と。パクチーはもちろん。写真はパカナ炒めご飯ですが、このパカナも松代のマリーさんの畑が産地。中にはプランターで育てて売りに来る人もいて、チェリーのスタッフは「農薬使ってないから安全」と言っていますが、ただし、時によって太さも味もマチマチなんですね。でもこのマリーさんは、スーパーのお惣菜のアルバイトの傍ら、かなり本格的な農業を営んでいて味も良し。ご主人は日本でタイ米が作れないかと模索して、諦めたみたいですけど。実はチェリー農場を営んでそれをレストランで提供したいと当初から考えているんですが、とてもじゃないが今のところはムリ。でもタイ人ネットワークからの供給でかなりまかなえているみたいです。作り手と食べる人を結ぶのも役目。たまにフリーペーパー等で取材にいらっしゃる方が「食材はタイから空輸」などと書いて下さって、確かに日本で入手できないものはしょうがないですが、地元で入手可能なら当然地元優先です。唐辛子とニンニクを効かせた夏野菜、お勧めです!
2008年08月07日 Posted by namfon at 23:13 │Comments(0) │食材の話題
パパイヤの問題
 「宮崎県のパパイヤにしようか」とバーン・チェリーのスタッフが話し合っていました。宮崎県→1個何万円のマンゴーという連想に進む私は「そんな高いパパイヤでこの値段でできるの?」と疑問を呈したところ「タイのパパイヤも高くてやり切れない」ということ。「じゃあ、沖縄にすれば、その方が安くない?」と私。ただこれは未確認の、部外者によるなんとなくの想いだけ。それなのに「じゃあ沖縄にするか」で話しが終わったのはいかにもタイ人風でもあります。その場がみんなタイ人と半人前の日本人じゃあこうなりがち。宮崎県がパパイヤの販路拡大に乗り出しているようで宣伝が送られてきたのだそうです。
「宮崎県のパパイヤにしようか」とバーン・チェリーのスタッフが話し合っていました。宮崎県→1個何万円のマンゴーという連想に進む私は「そんな高いパパイヤでこの値段でできるの?」と疑問を呈したところ「タイのパパイヤも高くてやり切れない」ということ。「じゃあ、沖縄にすれば、その方が安くない?」と私。ただこれは未確認の、部外者によるなんとなくの想いだけ。それなのに「じゃあ沖縄にするか」で話しが終わったのはいかにもタイ人風でもあります。その場がみんなタイ人と半人前の日本人じゃあこうなりがち。宮崎県がパパイヤの販路拡大に乗り出しているようで宣伝が送られてきたのだそうです。それでパパイヤを使ったメニューとは何かという問題ですが、それはส้มตำ=ソムタムです。フルーツとして食べるには熟したのが年中タイにはありますが、熟さないうちは野菜みたいに料理に使います。ソムタムは東北地方の郷土料理。青パパイヤをたたいて削って細くしてミニトマトなどを加えて混ぜて酸っぱく辛くします。チェリーのオーナーもこれまでのコックさんもみんな東北地方出身なので、子供の時から作っている得意中の得意料理で、私も最も好きなタイ料理に入れたいもの。ただし通常のお店で提供しているのは都市風ソムタムで区別のために「ソムタム・タイ」としています。違いは何かというと、都市風は干しエビやピーナッツを入れてマイルドで、郷土料理の味の決め手となる小魚を発酵させた独特の調味料を使いません。私はもっぱら郷土料理の方ばっかりで「こっちも紹介すればいいのに」と提案するのですが「こんな臭いの、日本人は食べない」と思い込んでるフシもあります。実はそんなことはなくて、もっともっと強烈な沢蟹入りをリクエストする日本人のお客さんもいて、ここはどこ?って感じです。
2008年07月15日 Posted by namfon at 12:40 │Comments(2) │食材の話題
パクチーは表面を繕う?
タイ料理というと“辛い”と一緒にイメージされるのが“ผักชีパクチー”のようで、お客さんの中には「パクチーを入れないで下さい」とおっしゃる方と「パクチーをたくさん入れて下さい」という方が両方いらっしゃいます。このリクエストに答えるのは他より簡単。パクチーの葉っぱは、たいていが料理の上に振りかけるだけだからです。主役にはならないということですね。実は隠れて活躍しているのは根っこの方で、スープストックにもヤムのソースにも潰して使われます。たまにスープの中に根っこらしきものが紛れ込んでいたら、それはパクチーの根です。ですから「パクチーの根を入れないで下さい」というリクエストですと、スープものは難しくなりますね。
タイに長年住んでいてもパクチーが苦手な日本人はいて、いつもいつも「マイ サイ パクチー ナ(パクチー入れないでね)」と頼んでいるのはごくろうさんって感じでした。このパクチーの用途がそのまま諺になっているので紹介します。それはผักชีโรยหน้า(パクチーローイナー)。ローイナーは美味しそうに見せるために表面に振りかけること。それで、表面だけを取り繕うとか、目先だけを飾っているぞ、という時に使います。アイツの仕事ぶりはパクチーローイナーみたいだ、という具合ですね。でもタイ人以外ではあの香りが苦手な人も多いわけですから、そうなると逆の意味にとられかねないような気もします。

タイに長年住んでいてもパクチーが苦手な日本人はいて、いつもいつも「マイ サイ パクチー ナ(パクチー入れないでね)」と頼んでいるのはごくろうさんって感じでした。このパクチーの用途がそのまま諺になっているので紹介します。それはผักชีโรยหน้า(パクチーローイナー)。ローイナーは美味しそうに見せるために表面に振りかけること。それで、表面だけを取り繕うとか、目先だけを飾っているぞ、という時に使います。アイツの仕事ぶりはパクチーローイナーみたいだ、という具合ですね。でもタイ人以外ではあの香りが苦手な人も多いわけですから、そうなると逆の意味にとられかねないような気もします。