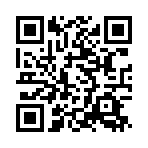辛い料理には生野菜が付き物
ここにあるのは、清涼感漂う香り豊かで私の大好きなパクチー・ラーオ(ラオスパクチー)とキュウリ以外は初対面。調べてみないといけませんね。野菜もハーブもアクも好きなので最初から抵抗はありませんでしたが、ちょっとびっくりしたのはバナナの花です。パッタイの付け合せに欠かせないものですが、栗の渋だけで花にしたような強烈な渋さ。最初はびっくりしました。アクとガンの関係も取りざたされたこともあったな、などと。きっと苦手な方には辛い食生活だと思いますが、アク抜きするのがもったいないと感じたことがあったり、アクの強い山菜や野草が好きという方ならタイ料理好きの素質は充分だと思います。
2009年06月22日 Posted by namfon at 21:19 │Comments(6) │タイ料理の話
東北地方独特の腸詰豚ソーセージ
バンコクの屋台で、豪快な煙を上げて炭火で焼きながら売っているのをビニール袋に入れてもらって、歩きながら唐辛子とニンニクとキャベツの葉っぱをかじりながら、このソーセージを食した思い出に浸りながら、東北地方を巡る旅の途中の川辺のしゃれたレストランで注文してみました。メニューには書いてなかったんですが「食べたい」と言ったら出してくれたもの。こういう融通はタイでは常識。チェリーでも材料がある限りはタイの常識で営業しています。このソーセージの特徴はモチ米を入れて発酵させていることで、だから酸味があるのです。白い粒々を最初は豚の脂身だと思っていました。米を入れていると知った時は、貧しいから米で増量しているのかと思いました。ニンニクが入っている上に、ニンニクやらショウガを付け合せるのもいかにもタイ。ビールのつまみに最高です。チェリーではメニューには入れていませんが、時々あります。北部には東北とは違った種類の「サイ・ウア」というのがあって、これもまた最高なんですよね。
2009年06月21日 Posted by namfon at 12:01 │Comments(0) │タイ料理の話
パッタイって何か分らなくなりました
 直訳すると「タイ炒め」の「パッタイ」を好きな方は多く、たまには他をどうですか、と言いたくなるくらいに、こればかり注文する方もいます。そういうひとりに、タイのおみやげの即席パッタイを渡したら「美味しかった」というメッセージと一緒に写真が送られてきました。なかなか美味しそうにできていて、味見できなかったのが残念。各種インスタントタイ料理がいろいろなメーカーから発売されていて、一昔前では考えられないタイ料理の普及ぶりと利便性には目をみはるばかりです。
直訳すると「タイ炒め」の「パッタイ」を好きな方は多く、たまには他をどうですか、と言いたくなるくらいに、こればかり注文する方もいます。そういうひとりに、タイのおみやげの即席パッタイを渡したら「美味しかった」というメッセージと一緒に写真が送られてきました。なかなか美味しそうにできていて、味見できなかったのが残念。各種インスタントタイ料理がいろいろなメーカーから発売されていて、一昔前では考えられないタイ料理の普及ぶりと利便性には目をみはるばかりです。ネットで作り方を検索したらたいていのタイ料理は作れてしまう世の中でもありまして、そのせいで湧き上がっている疑問がこのパッタイについてです。作り手によって作り方にバリエーションがあるのは当然とはいえ、それにしてもパッタイと呼ぶのはタマリンドの絞り汁を入れるもの、との思い込みが覆されつつあるのです。タマリンドのおかげで甘みとほのかな酸味の風味が出るわけで、もちろんチェリーではオリジナルソースを作って正統派(?)パッタイをお出ししています。でもタマリンドなしの炒め麺の作り方が「パッタイ」としてブログなどで紹介されていますし、お店によっても同様。何をもってパッタイと呼ぶか、思い込みを検証してみようと思います。いずれにしろ食べ比べてお好みを選べるようになったのは楽しいことです。
2009年06月20日 Posted by namfon at 17:12 │Comments(0) │タイ料理の話
タイ料理の4区分
タイの書店でまさに「4つの地方料理」という本を見つけたので買ってきました。「タイ人は身近で入手できる食材を使うので地方色が豊か」から始まります。北部は海から一番遠いので海魚は使いません。あまり辛みは強くなく、野菜の自然の甘みを利用する。東北地方は川魚や昆虫色も盛んなので匂い消しの意味もあって香草や唐辛子を多用。南部はシーフードを使って辛みが強め。中部は海もあって穀物地帯でもあり食材が豊富で料理も多彩。そんな特徴を頭の隅においてタイ料理店のメニューを見てみると、その店の方針というか得意分野が想像できて、楽しみも一段アップすると思います。ちなみに写真は分類したら中部料理のゲーン・リエン。魚のダシでショウガ味の効いた野菜と香草たっぷりのスープ。日本では作りにくいのが残念です。
2009年06月14日 Posted by namfon at 14:06 │Comments(0) │タイ料理の話
日本人はカレー味がお好き?
日本のカフェにもありそうな白い器。ココナツミルクの入ったカレースープに揚げた麺ですから、薬味を入れてライムを搾ってもやはりちょっとしつこい感じです。辛みも足りない。若い人にはいいのかもしれませんが、しばらくお腹が重たくなりました。日本語のタイ料理本を見ていたら「私の知っている日本人でカーオ・ソーイを嫌いな人はいません」というタイ人の著者のコメントが…。カレー味は確かに日本人には人気がありました。シーフードレストランだと「カニのカレー炒め」が代表。これはバーン・チェリーにもあって、ボリューム満点なので数人のグループだったら特にお勧めです。カニをエビに変えることもできます。
2009年06月08日 Posted by namfon at 20:18 │Comments(0) │タイ料理の話
グリーンカレーとロティのセット
今回のタイの旅で大変印象的だったのはご飯です。日本に入ってくるタイ米は香り米、あるいはジャスミンライスと呼ばれる最高級ブランドで、タイ米の中では比較的粘り気があります。チェリーでももちろんこれを使用していて、それに慣れてしまったせいか、タイで食べたお米が極端にパサパサで美味しくないと感じてしまい、タイ人の友人に話したら「だってタイ人はパサパサの方が好きだから」と言われました。それはよく言われることですが、ここまで極端だったかなと記憶をたどってみるものの、もう思い出せません。タイでは小麦粉の主食は一般的ではなかったですが、変化していくんだろうなとタイ料理店でのロティを見て感じました。
2009年05月30日 Posted by namfon at 08:58 │Comments(0) │タイ料理の話
初めて食べたフルーツのソムタム
「ソムタム・ポラマーイはどう?」と聞かれて日本からの2人は「何それ?」。名前からフルーツのソムタムであることは分りますが、通常ソムタムといえば青パパイヤで作るものを呼ぶのではなかったか。あるいは人参のソムタムは昔からありましたが。やはり浦島太郎状態。何年か前にバンコクから遊びに来た友達に「リンゴのソムタムが流行っている」と言われたことがありましたが、同類ですね。パパイヤ以外では、ザボン、グアバなどが入っています。フルーツなのでどうしても甘めになってしまって物足りない感じではありましたが、これを見てリンゴのソムタムのイメージは沸きました。シーズンになったら試作してみたいものです。
2009年05月29日 Posted by namfon at 20:27 │Comments(1) │タイ料理の話
タイの屋台料理って何でしょう
タイの市場や露店には、写真のように作りおきしたおかずを売る店が多いのですが、それよりも注文に応じてその場で作った方が熱々で美味しい、という趣旨だったのです。趣旨通りに、紹介されている料理はサッと作れるお馴染みの料理ばかり。もちろん購入してきました。そこで屋台料理に戻りますが、屋台でも、あらかじめおかずを用意して、客が選ぶのをその場で出したりテイクアウトできるスタイルも、注文に応じてサササと作るスタイルもあります。前者は「カーオ・ゲーン」といいます。ぶっかけご飯のことですね。チェリーの場合は後者ですが、実はランチタイムをカーオ・ゲーンスタイルでやりたいなと考えたこともあるのです。これぞ屋台というイメージで。しかし、これは人の多い所でないと難しいですね。
2009年05月11日 Posted by namfon at 09:33 │Comments(0) │タイ料理の話
バンコクの超高級デパ地下のフードコート
2009年05月10日 Posted by namfon at 21:08 │Comments(0) │タイ料理の話
星卵を載せていただくバジル炒めご飯
 始めてしまったからには2個というわけにもいかず、タイレストランの店名から覚えるタイ語解説です。どれにしようかなとガイドブックをめくっていたら「ダオタイ」というのがありました。タイ語表記がないけど多分ดาวไทยに違いない。素直にカタカナにするとダーオ・タイで、ダーオが星で、それにタイ国のタイで、つまりタイの星、タイのスターです。ダーオは女の人の名前にもよくあります。料理と関係する星といえばไข่ดาว(カイ・ダーオ)ですね。カイは卵だから星卵、日本風に言うと目玉焼きです。
始めてしまったからには2個というわけにもいかず、タイレストランの店名から覚えるタイ語解説です。どれにしようかなとガイドブックをめくっていたら「ダオタイ」というのがありました。タイ語表記がないけど多分ดาวไทยに違いない。素直にカタカナにするとダーオ・タイで、ダーオが星で、それにタイ国のタイで、つまりタイの星、タイのスターです。ダーオは女の人の名前にもよくあります。料理と関係する星といえばไข่ดาว(カイ・ダーオ)ですね。カイは卵だから星卵、日本風に言うと目玉焼きです。目玉焼きというネーミングも傑作だと思いますが、星卵も星4つくらいあげたい情緒がたっぷりです。写真はバーン・チェリーのメニューで鶏肉のバジル炒めご飯に星卵を載せたもの。バンコクにいる時はランチにしょっちゅう食べていました。バジル炒めは結構辛目なので、それが星卵で和らいでコクがでて一層美味しいんです。食欲なくてもこれなら食べられました。鶏肉じゃなくて豚にしたりイカにしたりエビにしたりも自由。この星卵は油の中に落とすので日本風に言うと揚げ卵ですかね。黄色の目玉部分が白くなるのでどっちかっていうと星というよりも、朧月夜のお月様みたいにも思えます。
2008年08月03日 Posted by namfon at 18:41 │Comments(2) │タイ料理の話
イエロー・カレーとは?
 タイから戻って間もなくの頃ですから10年も前ですが、新聞の広告でタイ料理店を見つけ、とうとう日本人向けの店ができたのかと喜ばしく思って早速行ってみました。するとランチメニューの中に「イエロー・カレー」というのがありました。えええ…!このカレーには辛い思い出があります。バンコクに住んでいた時に、住んでいた家の近所の人がカレーを持って来てくれました。แกงเหลือง(ゲーン・ルアン)つまりイエロー・カレーです。ただし、日本語ではゲーンのことをカレーと訳しているものの、タイ語だとスープ類はどれもゲーンですから、本当はスープと言った方がタイ料理の感覚には近いですね。それはともかく、そのカレーですが、猛烈に辛い。タイ人も驚く辛党の私もびっくりでした。作って持ってきてくれた女性はタイ南部の出身者で、それが郷土料理で、南部の料理が辛いことを知ったのはその時です。当然私の頭の中にはイエロー・カレー=恐ろしく辛いというイメージが定着しました。そのカレーが長野のタイ料理店にある…?
タイから戻って間もなくの頃ですから10年も前ですが、新聞の広告でタイ料理店を見つけ、とうとう日本人向けの店ができたのかと喜ばしく思って早速行ってみました。するとランチメニューの中に「イエロー・カレー」というのがありました。えええ…!このカレーには辛い思い出があります。バンコクに住んでいた時に、住んでいた家の近所の人がカレーを持って来てくれました。แกงเหลือง(ゲーン・ルアン)つまりイエロー・カレーです。ただし、日本語ではゲーンのことをカレーと訳しているものの、タイ語だとスープ類はどれもゲーンですから、本当はスープと言った方がタイ料理の感覚には近いですね。それはともかく、そのカレーですが、猛烈に辛い。タイ人も驚く辛党の私もびっくりでした。作って持ってきてくれた女性はタイ南部の出身者で、それが郷土料理で、南部の料理が辛いことを知ったのはその時です。当然私の頭の中にはイエロー・カレー=恐ろしく辛いというイメージが定着しました。そのカレーが長野のタイ料理店にある…?疑問に思ってオーナーらしき日本人男性に尋ねてみました。「これはどういうカレーですか」って。答えは「黄色いカレーです」のみ。勇気を出して注文したところ、確かに黄色いけど辛くないのがきました。ううん、馴染みのない味。そのお店はじきになくなってしまったのでどういう料理だったのかうかがう機会は逸してしまったのですが、一般的にはイエロー・カレーはグリーン・カレーやレッド・カレーよりも辛いと思っていただいて間違いないです。黄色はขมี้น(カミン)つまりウコンの色。体に良さそうですが、あそこまで唐辛子を入れたら相殺されちゃいそうです。残念ながらバーン・チェリーの標準メニューにはないんですけどね。隠れメニューには…どうでしょうか。公式メニューにあるのはグリーン・カレーとレッド・カレー。この違いは何でしょう。よく「どっちが辛いですか」と質問されるお客さんがいらっしゃいますが、そういう問題じゃあないんですね。
2008年07月19日 Posted by namfon at 23:20 │Comments(0) │タイ料理の話
ラーメンの麺のいろいろと量
 タイの屋台は朝は朝食用、昼はランチ用、夜は夕食用と入れ替わることも多いのですが、時間と場所を問わずによく見かけるのはラーメンの屋台です。バンコク在住時「昔はいろんな屋台があったのにラーメンばっかりになっちゃったね、楽で稼げるからかな」と残念がる日本人の声も聞きました。日本でラーメンというと小麦粉の麺が一般的ですがタイだと米の麺が優勢でก๋วยเตี๋ยว(クイティアオ)と言います。これの太麺、細麺、極細麺のスリーサイズ用意して、さらに店によっては小麦粉の麺บะหมี่(バーミー)も置いています。ですからただ「クイティアオ下さい」と注文しても作り手はとまどいます。「細麺の汁麺」とか「極細麺の汁なし」とか具体的に言うのが正解。もっともタイ語が分からないと分かれば適当に作ってくれますけどね。
タイの屋台は朝は朝食用、昼はランチ用、夜は夕食用と入れ替わることも多いのですが、時間と場所を問わずによく見かけるのはラーメンの屋台です。バンコク在住時「昔はいろんな屋台があったのにラーメンばっかりになっちゃったね、楽で稼げるからかな」と残念がる日本人の声も聞きました。日本でラーメンというと小麦粉の麺が一般的ですがタイだと米の麺が優勢でก๋วยเตี๋ยว(クイティアオ)と言います。これの太麺、細麺、極細麺のスリーサイズ用意して、さらに店によっては小麦粉の麺บะหมี่(バーミー)も置いています。ですからただ「クイティアオ下さい」と注文しても作り手はとまどいます。「細麺の汁麺」とか「極細麺の汁なし」とか具体的に言うのが正解。もっともタイ語が分からないと分かれば適当に作ってくれますけどね。もうひとつ大きな違いは全体の量です。日本のラーメンも今ではタイにすっかり浸透していて、チェーン展開するラーメン専門店も賑わっていますが、バンコクに登場した当初のタイ人の驚きは「日本のラーメンって量が多いねえ」でした。1人じゃあ食べきれないと言うのです。量を比較したら、タイのラーメンの2~4倍くらいはあるんじゃないかと思います。少ないとおやつ代わりにできたり、気に入ったらおかわりして食べたり、何店か食べ歩いたり、ご飯物も食べたい時には便利。日本のタイ料理店で、タイ風に少量のラーメンを今のところ見たことないです。バーン・チェリーも量は日本風で提供しています。野菜をたくさんにしてもらって、私もしょっちゅう食べてます。あっさりのクリアスープで美味しいです。
2008年07月09日 Posted by namfon at 15:29 │Comments(0) │タイ料理の話
何か足したくなるタイ人の習性
バーン・チェリーはタイ人がやっている店ですから、もちろんタイスタイルです。よく「これは辛いですか」と尋ねる方がいらっしゃいますが、つい「辛さはいかようにも調節します」と言うと、逆にとまどってしまう人も多く、それも混乱の元かと思って控え気味。作る前にいろいろ注文つけた上に、作った後も、味見する前にいきなり砂糖や唐辛子や酢を大量に入れるタイ人を見ていると、作る前の注文は何だったんだと思ったりもします。味の好みはそれぞれだと思いますが、タイ料理の店だったら砂糖、唐辛子入りナムプラー、乾燥一味唐辛子、唐辛子を漬けた酢の調味料セットは必ずあるはず。しっかり味はついているんだから使わなくてもいいんですが、タイ人だと何か足すのは癖みたいですね。だから出前を頼まれて、小さなプラスチック袋に料理に合わせた必要調味料を添付するのを忘れると、あり得ない!って顔をされます。
2008年07月06日 Posted by namfon at 14:57 │Comments(0) │タイ料理の話
アメリカ人はパッタイがお好き?
 タイ国内を旅行中、ミャンマーとの国境の町に行った時に知り合ったアメリカ人男性が「僕はヘルスコンシャスだからタイ料理は好きなんだ」と言って、特にผัดไทย(パッタイ)がお気に入りだということでした。辛いものばかり食べていた私としては、タイ料理が健康的であるとも思えなかったのですが、パッタイが健康食だなんてもっと意外です。パッタイというのは、ผัดパッが「炒める」ไทยがタイ、すなわちタイ国のタイですから「タイ炒め」という栄誉ある名前の、いわばヤキソバです。大方のタイ料理がそうであるように米麺で、ソースにタマリンドの汁を絞って甘酸っぱさを出すのが特徴です。バーン・チェリーではこの複雑なソースを手作りしてますから日本にいながら本場の味をお楽しみいただけますよ。こればっかりご注文の方もいらっしゃるほどの人気メニューですが、超辛党の私は3年に1度食べるかどうかの頻度で、実はあまり知ったかぶりできませんけど…。
タイ国内を旅行中、ミャンマーとの国境の町に行った時に知り合ったアメリカ人男性が「僕はヘルスコンシャスだからタイ料理は好きなんだ」と言って、特にผัดไทย(パッタイ)がお気に入りだということでした。辛いものばかり食べていた私としては、タイ料理が健康的であるとも思えなかったのですが、パッタイが健康食だなんてもっと意外です。パッタイというのは、ผัดパッが「炒める」ไทยがタイ、すなわちタイ国のタイですから「タイ炒め」という栄誉ある名前の、いわばヤキソバです。大方のタイ料理がそうであるように米麺で、ソースにタマリンドの汁を絞って甘酸っぱさを出すのが特徴です。バーン・チェリーではこの複雑なソースを手作りしてますから日本にいながら本場の味をお楽しみいただけますよ。こればっかりご注文の方もいらっしゃるほどの人気メニューですが、超辛党の私は3年に1度食べるかどうかの頻度で、実はあまり知ったかぶりできませんけど…。その時からアメリカ人はパッタイがお好きなんだろうかという疑問がくすぶっておりまして、アメリカ人に会う機会があると尋ねているんです。まずは「タイ料理好きですか?」と聞くとたいてい「好き、好き」と言うので「何が好き?」と。それで、サンプル数膨大とは言えませんが、今のところ100%「パッタイ」です。日本ではトムヤムクンが、アメリカではパッタイが人気であるようなのはなぜでしょうか。あと、アメリカに住んでいた日本人にも聞いたら同じ答えだったです。お店にはいろいろなお国の方がいらっしゃいますので今後も聞き取りは続けてみたいと思います。アメリカ人とパッタイの関係をご存知の方がいらしたら教えて下さい。パッタイの写真、近いうちに用意します。
タグ :タイ料理
2008年07月05日 Posted by namfon at 13:56 │Comments(0) │タイ料理の話
トム・ヤム・クンのちょっと解説
日本で有名なタイ料理といえばต้มยำกุ้ง=トム・ヤム・クンみたいです。有名になった経緯を知りたいものですが、バンコクから帰ってきて、タイ料理の代名詞みたいになっていることを知ったものですから検証できないまんま。さすがにここまでタイ料理が一般化すると見かけなくなったものの、以前は「トムヤンクン」という表記も目立ちました。タイ語を知らなければどうということないんですけど、タイ語を知っているとヤンとヤムでは意味が全然違うことが分かってしまって胸をかきむしりたくなる感じです。だからって末子音のあるタイ語だとmuと母音入りで発音するわけではないんですけどね。この辺りはまた別項にて。
料理名を分解すると、トム=煮る、ヤム=混ぜる、クン=エビ、となります。となるとエビじゃなくてもいいでしょ、と思いますよね。その通りです。トムヤムというのは、マクルートの葉ใบมะกรูดとレモングラスตะไคร้(タクライ)とカーข่าというショウガ科の香辛料3種が入ったスープの呼称ですから、ここにエビを入れようが鶏肉を入れようがシーフードミックスを入れようが干魚を入れようが自由なのです。日本で作るならサンマをザクっと切って入れてもいけますよ。試したかったら「トム・ヤム・サンマ」と注文してみて下さい。バーン・チェリーだと、サンマのストックがあったら作ってくれること確実ですけど…タイ料理ではサンマを使わないから、予約した方がもっと確実です。それと、トムヤムは、お店によって味の違いが大きいです。豊富なハーブを入れて酸味と辛味と甘味のバランスをどう取るかですからね。バーン・チェリーのコックさんは、日本人にとっては味が濃い目かも。タイ人には評判いいんですけどね。薄味が好みなら「薄めにして」って日本語で言っていただければOKです。その場で手作りですから、いかようにも対応できます。いろんな店で味わって違いを実感されることをお勧めします。

料理名を分解すると、トム=煮る、ヤム=混ぜる、クン=エビ、となります。となるとエビじゃなくてもいいでしょ、と思いますよね。その通りです。トムヤムというのは、マクルートの葉ใบมะกรูดとレモングラスตะไคร้(タクライ)とカーข่าというショウガ科の香辛料3種が入ったスープの呼称ですから、ここにエビを入れようが鶏肉を入れようがシーフードミックスを入れようが干魚を入れようが自由なのです。日本で作るならサンマをザクっと切って入れてもいけますよ。試したかったら「トム・ヤム・サンマ」と注文してみて下さい。バーン・チェリーだと、サンマのストックがあったら作ってくれること確実ですけど…タイ料理ではサンマを使わないから、予約した方がもっと確実です。それと、トムヤムは、お店によって味の違いが大きいです。豊富なハーブを入れて酸味と辛味と甘味のバランスをどう取るかですからね。バーン・チェリーのコックさんは、日本人にとっては味が濃い目かも。タイ人には評判いいんですけどね。薄味が好みなら「薄めにして」って日本語で言っていただければOKです。その場で手作りですから、いかようにも対応できます。いろんな店で味わって違いを実感されることをお勧めします。